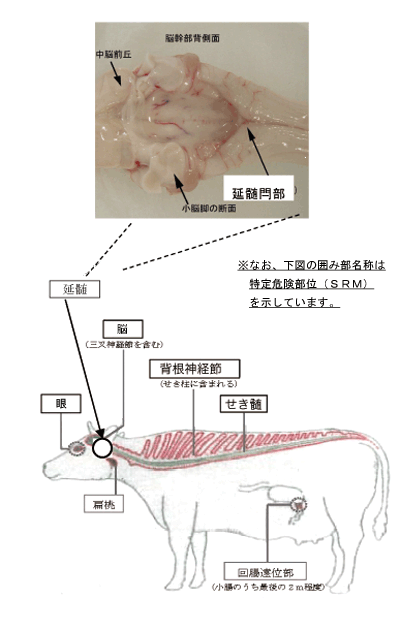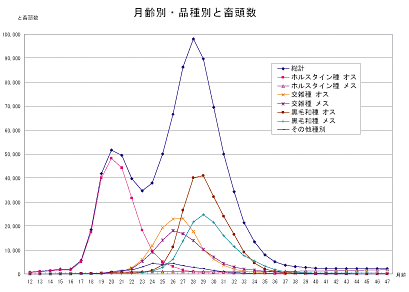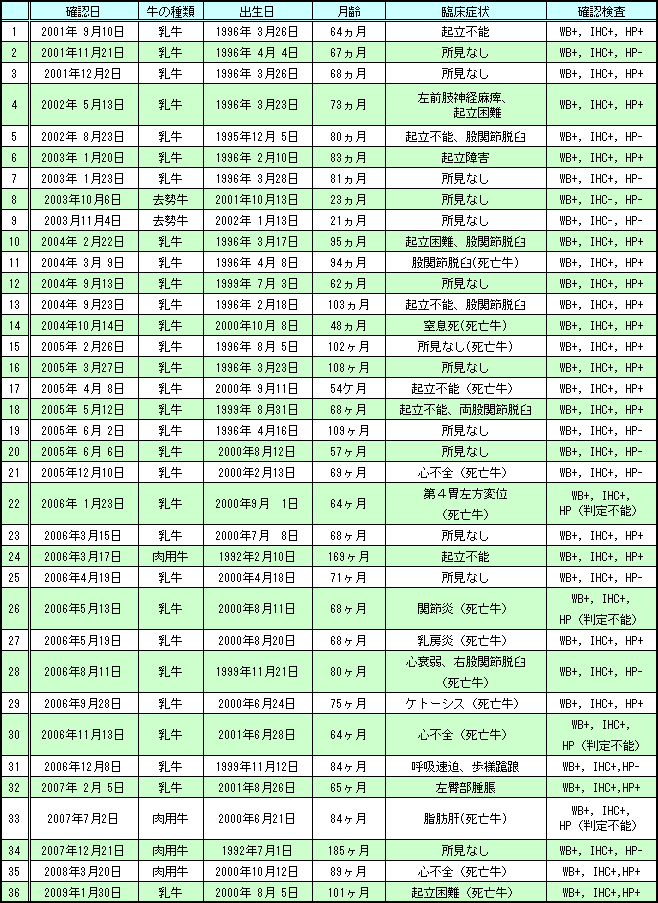食の安全ダイヤル
「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等について:BSE関係
最近の科学的知見はこちらをご覧下さい。
※(これらの回答は、過去の一時点の科学的知見を基にしています。)
V BSE関係
|
V-Q1.
|
BSE(伝達性海綿状脳症)に関する牛の背根神経節のリスクの評価について教えて下さい。(平成15年9月)
|
||
|
V-A1.
|
9月11日に食品安全委員会で評価が行われ、「背根神経節のリスクは脊髄と同程度と考えられる」とされました。これは背根神経節は脊髄と同程度のリスクがあり、背根神経節を含む脊柱については、より高い安全性を確保する点から特定危険部位に相当する対応を講ずることが適当であると考えられるとしております。
なお、このリスク評価結果に基づき、関係機関において適切なリスク管理措置が検討されています。
|
|
V-Q2.
|
「アルカリ処理をした液状の肉骨粉等を肥料として利用すること」に係る食品健康影響評価についてわかりやすく説明してください。(平成15年11月)
|
||||||||||||
|
V-A2.
|
|
|
V-Q3.
|
「牛せき柱を含む飼料及び肥料の規格等の改正」で食品安全委員会は「特定危険部位に相当する対応が必要」と評価しましたが、わかりやすく説明して下さい。(平成15年11月)
|
||||||||||
|
V-A3.
|
|
|
V-Q4.
|
アメリカでBSE牛が確認されましたが、米国産牛肉等に対して政府としてどのような対応をしているのですか。(平成15年12月)
|
|
V-A4.
|
平成15年12月24日に米国においてBSEが疑われる牛が発見されたとの情報を得て、同日より米国産牛肉の輸入を緊急停止し、同年12月26日にBSEであるとの診断が確定したことから、同日より米国産牛肉等について、食品衛生法第5条第2項に基づき輸入が禁止されました。
既に輸入され、国内に流通している米国産の牛肉及び牛肉等を用いた加工品については、特定部位が混入している又はそのおそれがあるものについて回収の指示が輸入業者に対して行われることとされています。 現在、検疫所において輸入状況の調査が実施されているところですが、特定部位の混入又はそのおそれがあるものが確認され次第、順次廃棄等の措置がとられることとなっています。 詳しくは、厚生労働省、農林水産省のホームページをご覧ください。 (http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/12/h1226-3.html  ) )(http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/bse/b_kaigai/  ) )食品安全委員会では、平成15年12月25日と平成16年1月8日の委員会において厚生労働省及び農林水産省から報告を受け意見交換を行っています。また、平成15年12月29日には、米国側から説明を聴取する等のための日米会合に関係省ともに出席しました。さらに、平成16年1月8日からの政府合同の調査チームの派遣に参加するなど各種情報の収集等に努めているところです。 |
|
V-Q5.
|
ウシ由来の原料がサプリメント等のカプセルに用いられていると聞きましたが、カプセルの主原料であるゼラチンの安全性について教えてください。(平成16年1月)
|
||||||||
|
V-A5.
|
ゼラチンは、主に牛の骨や皮などを原料にして製造されます。これらのゼラチンや原料については、
によって、一層の安全性確保がなされることになります。なお、厚生労働省が行った平成15年8月の実態調査によれば、牛骨ゼラチンに国産のせき柱を使用する実態はないとの結果が得られています。
|
|
V-Q6.
|
米国のBSE発生に関し現地調査団に委員会からも参加したということですが、調査団の報告について、わかりやすく教えてください。(平成16年1月)
|
||||||||||||||||||||||||
|
V-A6.
|
今回の調査団には、食品安全委員会事務局からも職員1名が参加しました。調査団は、米国で発生したBSEについての事実関係及び米国等のBSE対策について調査することを目的に、1月8日から18日までの日程で、米国及びカナダの政府機関や食肉処理施設などを訪問しました。
今回、米国で確認されたBSE感染牛は、カナダ・アルバータ州の牧場で1997年に生まれ、2001年に米国に輸入されたものです。米国は、カナダと協力しながらカナダから感染牛と一緒に米国に輸入された牛や、感染牛が生まれた農場で同時期に育てられていた牛、感染牛が産んだ牛などの追跡調査を行ってまいりました。 また、米国におけるBSE対策については、以下の通り報告されています。
最後に、今回の調査のまとめとして以下の事項が指摘されています。
なお、調査団の報告の内容については、「米国でのBSE発生に伴う海外調査について」
(http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20040120sfc) をご覧ください。 |
|
V-Q7.
|
米国でのBSE発生への対応については、科学的な知見に基づいた議論が必要と考えますが、食品安全委員会では検討がなされているのでしょうか。(平成16年2月)
|
|
V-A7.
|
食品安全委員会としては、米国におけるBSEの発生に対し、正確な事実関係の把握が重要と考え、発生直後、農林水産省及び厚生労働省から委員会の場で対応状況について報告を求めました。同時に、合同調査団への参加、各種海外情報収集など、情報の収集及び分析に全力を挙げております。
また、厚生労働省及び農林水産省から輸入再開について意見を求められることも想定し、プリオン専門調査会を3回にわたって開催し、米国のBSEに関する国際調査団の団長を招くなど、米国のBSEの状況について議論を深めております。今後も、米国との協議の状況も踏まえながら、専門調査会等で議論をさらに進めていきたいと考えています。 |
|
V-Q8.
|
海外でのBSE発生国とvCJDの発生国について教えてください。(平成16年3月)(平成24年1月更新)
|
|
V-A8.
|
BSE(牛海綿状脳症)については、英国をはじめとする欧州諸国21ヶ国とカナダ、イスラエル、日本、米国の計25ヶ国で自国産牛での発生が確認されています。また、オマーン、フォークランド諸島において、自国産牛ではなく輸入牛での発生が確認されています。
BSEの発生件数をみると(2012年1月16日時点)、英国が約18.4万頭と圧倒的に多く、次いでアイルランド1,651頭、ポルトガル1,077頭、フランス1,018頭、スペイン779頭、スイス466頭、ドイツ419頭となっています。 (OIE(国際獣疫事務局)調べ:2012年1月16日現在)
vCJD(変異型クロイツフェルト・ヤコブ病)については、これまで世界全体で225人の患者が確認されていますが、そのほとんどが英国(176人)に集中しています。この他では、フランス(25人)※1、スペイン(5人)、アイルランド(4人)※1、米国(3人)※3、オランダ(3人)、イタリア(2人)、ポルトガル(2人)、カナダ(2人)※1、日本(1人)※2、サウジアラビア(1人)、台湾(1人)※2で発生が確認されています。
(※1:英国滞在歴のある患者を含む。 ※2:英国滞在歴のある患者 ※3:在米英国人、及び在米サウジアラビア人) (Department of Health(英国保健省)等調べ:2011年10月11日現在)
|
|
V-Q9.
|
米国でのBSE発生への対応については、科学的な知見に基づいた議論が必要と考えますが、食品安全委員会ではどのような検討がなされているのでしょうか。(平成16年4月)
|
|
V-A9.
|
米国におけるBSEの発生に対しては、正確な事実関係の把握が重要と考え、発生直後から情報の収集及び分析に努めるとともに、2月初め以降数回にわたるプリオン専門調査会において、収集された情報に基づき議論を深めてまいりました。さらに、議論するにあたって必要となる情報・データ等を米国政府に求め、提供された情報等の整理・分析を進めているところです。
一方、日米BSE協議によって設置されることとなったワーキンググループで米国産牛肉の輸出入に係る技術的・専門的事項についての協議を行うこととなりました。中立公正な立場にある食品安全委員会は、オブザーバーとして参加することとなりますが、協議の内容を注視し、情報収集に努めてまいります。 いずれにしても、引き続き、幅広い情報収集を行うとともに、BSE全般について科学的、客観的に議論してまいります。 |
|
V-Q10.
|
牛の腸全体の安全性について教えて下さい。(平成16年6月)
|
||||||
|
V-A10.
|
これまでの知見として、BSE発症牛の各組織をマウスや牛に接種した試験や、各組織の異常プリオンたん白質の蓄積を検出する試験などの結果から、回腸遠位部には感染性や異常プリオンたん白質が認められたものの、それ以外の腸(十二指腸、空腸、遠位部以外の回腸、盲腸、大腸)や、食道及び胃(第1胃から第4胃)において感染性又は異常プリオンたん白質は認められていません。
現在、日本では、牛の回腸(盲腸との接合部から2m)については、頭部(舌及び頬肉を除く)及びせき髄とともに、と畜場で除去・廃棄されています。 なお、本年5月に開催された国際獣疫事務局(OIE)の総会において、BSEに係る牛の特定危険部位について、従来の6ヶ月齢を超える牛の回腸遠位部から全月齢の牛の腸全体に変更することが決定されました。しかしながら、この決定に関し、科学的な根拠として回腸遠位部以外の腸に感染性が認められたというような新しい知見が示されたわけではなく、厚生労働省は、現時点で規制を見直すことは考えていないとしております。
|
||||||
|
V-Q11.
|
食品安全委員会で我が国におけるBSE対策全般についての科学的な検証が行われているとのことですが、どのような議論がされているのですか。(平成16年7月)
|
|
V-A11.
|
食品安全委員会においては、平成15年8月の第1回プリオン専門調査会において、「日本のBSE問題全般について議論することが重要である」とされ、本年2月から種々の情報収集、海外専門家からの意見聴取などを行い、調査審議を進めてきており、7月16日の第12回専門調査会において、日本における牛海綿状脳症(BSE)対策について報告書たたき台の審議がなされたところです。
本たたき台にも示されているとおり、ここでの審議は、「わが国でBSE感染牛が確認されて2年半が経過し、・・・現在までに得られたデータや知見を踏まえ、vCJDのリスクの低減効果から、わが国におけるBSE対策(管理措置)をレビューし、今後の対策に活用することが重要」との考えから検証しているもので、見直しを前提とするものではありません。 |
|
V-Q12.
|
BSEについては、異常プリオンがその原因と考えられるようですが、なぜ、危険部位にしか蓄積しないのですか。例えば、血液や牛乳には含まれることはないのですか。(平成16年7月)
|
|
V-A12.
|
現在までの知見では、異常プリオン蛋白は、特定危険部位(SRM)とされる脳、目を含む牛の頭部(舌及び頬肉を除く。)、せき髄、回腸遠位部、背根神経節にBSE感染牛の体内の99%以上が蓄積されていることが分かっております。なお、英国でBSE感染牛の各組織をマウスの脳内へ接種した実験でも、筋肉、心臓、肝臓、肺、食道、胃、小腸(近位、遠位)、結腸(近位、遠位)、直腸、血液、乳などでは感染性が検出されていません。
|
|
V-Q13.
|
「中間とりまとめ」のポイントを分かりやすく説明してください。(平成16年9月)
|
||||||||||
|
V-A13.
|
食品安全委員会では、日本における牛海綿状脳症(BSE)対策について、プリオン専門調査会を中心として検証を行い、9月9日に「中間とりまとめ」を取りまとめ、同日、厚生労働大臣及び農林水産大臣に通知いたしました。
本中間とりまとめの主なポイントは以下のとおりです。
|
|
V-Q14.
|
BSE検査の検出限界以下の量でもBSEプリオンを食品を通じて摂取することにより、vCJDの発症の可能性があるのかどうか教えてください。(平成16年9月)
|
||||
|
V-A14.
|
現在の知見では、
|
|
V-Q15.
|
「中間とりまとめ」とされていますが、「中間」とはどういうことですか。(平成16年9月)
|
|
V-A15.
|
BSE問題を科学的に検証することは食品安全委員会の責務であると認識し、発足以来、プリオン専門調査会を中心にBSE問題全体について幅広く情報・データを収集・整理するとともに、様々な角度から綿密な検討を続け、「日本における牛海綿状脳症(BSE)対策について」の現時点の取りまとめとして中間とりまとめに至ったものです。
一方、中間とりまとめにも記述されているように、今後とも日本におけるBSEによるリスクの定量的な評価等を行うことが課題とされており、必要な情報の収集を進め、引き続き議論を着実に行ってまいりたいと考えております。 |
|
V-Q16.
|
350万頭の牛についてBSE検査を行ったとされていますが、それらの牛の月齢は把握されているのですか。また、20ケ月齢以下の牛がどれくらいいたのですか。(平成16年9月)
|
|
V-A16.
|
わが国においては、従来より出生情報等が整備されており、約3年間にと畜された350万頭の牛の月齢分布が推定することができます。これによれば、20ヶ月齢以下の牛は全体の約1割と考えられます。
昨年12月からは「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」に基づき、生産・と畜段階において牛の出生情報等の個体識別のための情報を記録するトレーサビリティ制度が義務付けられ、正確な月齢の判定が確実にできるようになっています。 |
|
V-Q17.
|
プリオン専門調査会での審議と平行して開催されていた意見交換会等において指摘されてきた見解や意見については、取りまとめに当たってどのように対応されたのですか。(平成16年9月)
|
|
V-A17.
|
食品安全委員会は、我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策の検証作業について国民の皆様に理解を深めていただくとともに、関係者と意見を交換するため、科学的な議論を深める段階から積極的に意見交換会などのリスクコミュニケーションを実施してまいりました。
これらの意見交換会においていただいた意見については、プリオン専門調査会にご報告し、これらの意見も含めて議論を行って中間とりまとめを行ったところです。 |
|
V-Q18.
|
「vCJD」と「SRM」の省略しない綴りを教えてください。(平成16年10月)
|
||||
|
V-A18.
|
「日本における牛海綿状脳症(BSE)対策について-中間とりまとめ-」の中で用いられている「vCJD」と「SRM」の省略しない綴りについては、次のとおりです。
|
|
V-Q19.
|
BSE検査において、異常プリオンたん白質の有無を調べる牛の延髄閂部(えんずいかんぬきぶ)とは、どこにある部位なのか、教えてください。(平成16年10月)
|
|
|
V-A19.
|
下記の図のとおり、延髄部分は左側が小脳、右側が脊髄側へ伸びていく部位となっています。矢印で示した部位が延髄閂部です。
|
|
V-Q20.
|
日本では、どれぐらいの月齢で牛がと畜されるのが一般的なのか教えてください。(平成16年10月)
|
||
|
V-A20.
|
「日本における牛海綿状脳症(BSE)対策について−中間とりまとめ−」の資料によれば、月齢別と畜数をみると2つのピークがあります。1つ目のピークとして20ヶ月齢に主にホルスタイン種のオスによるピークがあり、2つ目のピークとして28ヶ月齢に1つ目の約2倍にあたると畜数のピークがあります。
|
||
|
注)
|
|
||
|
1)
|
原データについては、独立行政法人家畜改良センターの公表資料によるもので、平成15年度の個体識別全国データベースの集計結果です。詳しくは、同センターホームページ(https://www.id.nlbc.go.jp/
 )をご覧ください。 )をご覧ください。 |
||
|
2)
|
47カ月齢以上の牛についてもメスを中心にと畜されている
|
||
|
3)
|
6月10日集計。法施行が平成15年12月1日であるため、11月30日までにと畜された牛の情報はすべて法の対象外の報告であり、11月30日以前に出生し12月1日以降にと畜された牛は性別のみが法の対象となる届出(ただし、法施行に伴う再届出であり集計時点では確認中)、12月1日以降に生まれた牛は性別、生年月日とも法の対象となる届出に基づくものです。
|
|
V-Q21.
|
21、23ヶ月齢のBSE感染牛については、異常プリオンの検出量が微量であったとされるが、どの程度の量か教えてください。(平成16年11月)
|
|
V-A21.
|
21、23ヶ月齢で発見された2頭のBSE感染牛の延髄閂部に含まれる異常プリオンたんぱく質の量は、WB(ウエスタンブロット)法で調べた結果では、我が国で確認されたその他の感染牛と比較して500分の1から、1,000分の1の量と推定されています。
|
|
V-Q22.
|
「中間とりまとめ」に日本人の9割はプリオンたんぱく質遺伝子がM/M型であると記載されていましたが、そのこととvCJDの感染リスクの関連性について教えてください。(平成16年12月)
|
|
V-A22.
|
英国のvCJD患者の殆どが、プリオンたん白質遺伝子のコドン129がメチオニンの同型遺伝子型(メチオニン/メチオニン;M/M)を有していたことから、M/M型の人は他の型の人に比べ、vCJDの潜伏期間がより短く、かつ感受性がより強いか、またはそのどちらかであるとの報告があります。一方、我が国では、全人口に占めるM/M型の割合は、英国よりも高いとされ、91.6%であるとの報告もあります。なお、英国を含むヨーロッパの白人の約40%がMM型の遺伝子を持っているとの報告もあります。
なお、こうした事実関係を踏まえ、「中間とりまとめ」でのvCJD患者の発生数の推定に当たっては、この遺伝子要因も考慮に入れて計算しています。 しかしながら、人にBSEプリオンたん白質が感染して中枢神経にひろがっていくメカニズムについては、現時点で詳細な知見は得られておらず、現時点において、vCJDに関する遺伝子的要因と感染リスクの関連性について明確に説明することは出来ません。 |
|
V-Q23.
|
「中間とりまとめ」にある「交差汚染」についてわかりやすく教えてください。(平成16年12月)
|
|
V-A23.
|
飼料工場、販売店、そして農家等において、BSEプリオンたん白質に汚染されていない飼料に汚染された飼料が意図せずに僅かでも混入してしまうことです。
|
|
V-Q24.
|
「日本における牛海綿状脳症(BSE)対策について−中間とりまとめ−」において、vCJD発生リスクの推定が行われていますが、その推定の考え方について教えて下さい。(平成17年1月)
|
|
V-A24.
|
この「中間とりまとめ」では、英国のBSE感染牛、vCJD患者の推定数から日本におけるvCJD患者数を推定しています。
この考え方は、vCJD患者数はBSE感染牛(対策が講じられていなかったころに食用とされたと考えられるBSE感染牛)の頭数に比例すると仮定し、その関係を日本に当てはめ、日本で対策が講じられる以前に食用にされたと推定されるBSE感染牛の頭数から日本におけるvCJD患者数を推定するものです。 いくつかの不確実性をもった推定であることから、最も悲観的な結果となるような英国のBSE感染牛、vCJD患者の推定数を用いています。 詳しくは、「日本における牛海綿状脳症(BSE)対策について−中間とりまとめ−」 (http://www.fsc.go.jp/sonota/chukan_torimatome_bse160913.pdf  )を参照下さい。 )を参照下さい。 |
|
V-Q25.
|
vCJDの潜伏期間について教えてください。(平成17年2月)
|
|
V-A25.
|
食品安全委員会では、これまでの日本におけるBSE対策全般について検証を行い「日本における牛海綿状脳症(BSE)対策について-中間とりまとめ-」を平成16年9月に取りまとめたところです。
その中で、vCJDの潜伏期間については、「人にBSEプリオンが感染して中枢神経系に広がっていくメカニズムについては、時間的経過を含め、不明である。また、vCJDの潜伏期間の長さについても分かっていない。仮説では、数年から25年以上と幅広い。」とされています。 なお、「中間とりまとめ」の詳細につきましては、食品安全委員会ホームページ (http://www.fsc.go.jp/sonota/chukan_torimatome_bse160913.pdf  )をご参照ください。 )をご参照ください。 |
|
V-Q26.
|
食品安全委員会がBSEの国内対策の見直しについて昨年10月に評価要請を受けて以降、これまで食品安全委員会においてどのような議論がされているのか教えてください。(平成17年3月)
|
|
V-A26.
|
食品安全委員会においては、我が国でBSEが確認されてから約3年の間に蓄積されたデータや科学的知見を収集・整理し、それらに基づき、日本におけるBSE対策について議論を行い、昨年9月に「中間とりまとめ」として公表したところです。
この「中間とりまとめ」を踏まえ、昨年10月には厚生労働省及び農林水産省から、 [1] と畜場におけるBSE検査対象をすべての牛から21ヶ月齢以上の牛への変更 [2] 特定危険部位(SRM)の除去の徹底 [3] 飼料規制の実効性確保の強化 [4] BSEに関する調査研究の一層の推進 の4項目についての国内のBSE対策の見直しに関する評価要請(諮問)がありました。 プリオン専門調査会においては、諮問以降8回にわたって中立公正な立場から、科学的な議論を尽くした結果、去る3月28日の会合において、報告案が取りまとめられたところです。 本報告案においては、と畜場におけるBSE検査対象月齢を見直す場合については、その見直しにかかわらず、食肉の汚染度は「無視できる」〜「非常に低い」と推定され、この結果から、検査月齢の線引きがもたらす人に対するリスクは、非常に低いレベルの増加にとどまるものと判断される、とされています。 なお、本報告案については、3月31日の食品安全委員会において報告され、広く国民からの意見・情報の募集を開始したところであり、4月27日までの4週間の募集期間が終了した後、食品安全委員会において再度審議することになります。 |
|
V-Q27.
|
これまでのプリオン専門調査会での審議は国内のBSE対策についての安全性評価でしたが、米国産牛肉に関する評価への対応について教えてください。(平成17年3月)
|
|
V-A27.
|
米国産牛肉の輸入再開問題に関しては、評価要請を受けていない今の段階で、予断を持ってお答えすることはできませんが、いずれにしても、食品安全委員会としては従来どおり、食品健康影響評価については、中立公正な立場から科学的議論を尽くしてまいります。
|
|
V-Q28.
|
我が国や諸外国のBSE検査の陽性月齢について教えてください。(平成17年4月)(平成19年8月更新)
|
|
V-A28.
|
我が国においてBSE検査により陽性とされたものは、平成19年7月2日時点で、33頭確認しています。BSE検査で陽性となった牛の月齢は、21、 23、48、54、57、62、64、65、67、68、69、71、73、75、80、81、83、84、94、95、102、103、108、109、 169ヶ月齢です。
また、EU15ヶ国のアクティブ・サーベイランスにおけるBSE検査陽性牛の年齢分布(2005年データ 出典:※)は、2歳1頭、3歳6頭、4歳21頭、5歳57頭、6歳52頭、7歳47頭、8歳以上は340頭となっています。 ※ European Commission :Report on the monitoring and testing of ruminants for the presence of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) in the EU in 2005. (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/bse/annual_report_tse2005_en.pdf  ) ) |
|
V-Q29.
|
5月6日に、「我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策に係る食品健康影響評価」についての答申が食品安全委員会から出されましたが、そのポイントをわかりやすく教えてください。(平成17年5月)
|
|
V-A29.
|
我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しについては、平成16年10月15日に厚生労働省、農林水産省から以下の項目
[1]と畜場におけるBSE検査対象月齢の見直し及び検査技術に関する研究開発の推進 [2]特定危険部位(SRM)の除去の徹底 [3]飼料規制の実効性確保の強化 [4]BSEに関する調査研究の一層の推進 について、食品健康影響評価(リスク評価)の要請を受け、プリオン専門調査会において、8回にわたって、中立公正な立場から科学的な議論を尽くし、去る5月6日に食品安全委員会において、最終的な評価結果をとりまとめました。 この評価結果においては、と畜場におけるBSE検査対象月齢を見直す場合については、食肉の汚染度は全頭検査した場合と21ヶ月齢以上を検査した場合、いずれにおいても「無視できる」〜「非常に低い」と推定され、この結果から、検査月齢の線引きがもたらす人に対するリスクは、非常に低いレベルの増加にとどまるものと判断される、とされたところです。 詳しい内容は、食品安全委員会ホームページ (http://www.fsc.go.jp/sonota/bse_old.html)をご覧下さい。 |
|
V-Q30.
|
これまでに日本で確認されたBSE感染牛について、月齢と品種など、その概要について教えてください。(平成17年5月)(平成24年1月更新)
|
|||
|
V-A30.
|
厚生労働省及び農林水産省からの報告によれば、平成21年1月30日までに確認されている日本でのBSE感染牛は36頭で、月齢については、34頭の48ヶ月齢以上の牛と、21、23ヶ月齢の牛が確認されており、品種については、32頭がホルスタイン、4頭が黒毛和種となっています。
詳細は、下記概要のほか、厚生労働省の牛海綿状脳症(BSE)等に関するQ&Aを参照してください。 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bse/topics/tp010308-1.html#22q2  ) )
|
|
V-Q31.
|
1,000℃以上で、一定時間焼却処理した肉骨粉の焼却灰及び炭化物を肥料として利用することによるBSE汚染リスクは無視できると評価しましたが、わかりやすく説明してください。また、肥料としての肉骨粉の利用価値等についても教えて下さい。(平成17年8月)
|
|
V-A31.
|
肉骨粉の焼却灰及び炭化物の肥料利用におけるBSE汚染リスクの評価については、プリオン専門調査会において審議がなされ、この結果を受けて、本年7月28日の食品安全委員会で評価結果が決定されたものです。
本評価においては、耐熱性の高い羊スクレイピープリオンを用いて、1,000℃の熱処理で感染性が消失した実験データ及び800℃、30分間の熱処理が肉骨粉炭化物中のアミノ酸を消失させる分析データ等の科学的知見を基に審議が行われました。この結果、牛の特定危険部位(SRM)及び検査を経ていない牛の部位が混合しない、国内で製造される肉骨粉を、空気が流通した状態で、1,000℃、5分間以上の焼却処理された焼却灰、及び空気を遮断した状態で1,000℃、30分間以上の焼却処理された炭化物を肥料に利用することに係る人への健康影響は無視できるとされました。 また、肥料としての肉骨粉の利用に関し、農林水産省によれば、1,000℃以上で、一定時間焼却処理した肉骨粉の焼却灰と炭化物は、水稲、果樹、野菜等の農作物の緩効性肥料として、利用価値があるとのことです。 |
|
V-Q32.
|
プリオン専門調査会で米国・カナダ産牛肉等の安全性についての審議結果(案)が取りまとめられましたが、審議の経緯及び審議結果(案)のポイントについて教えてください。(平成17年10月)
|
||||
|
V-A32.
|
食品安全委員会は、厚生労働省及び農林水産省から、本年5月24日に米国及びカナダ産の牛肉及び牛の内臓について、食品健康影響評価(リスク評価)の要請を受け、食品安全委員会の下に設置されているプリオン専門調査会において、10回にわたって、公正中立な立場から科学的な議論を尽くし、審議結果(案)が取りまとめられたところです。
両省からの諮問内容は、現在の米国及びカナダの国内規制及び日本向け輸出プログラム(注)により管理され、輸入される牛肉及び牛の内臓を食品として摂取する場合と、我が国でとさつ解体して流通している牛肉及び牛の内臓を食品として摂取する場合のBSEに関するリスクの同等性です。 〔注:日本向け輸出プログラム[1]牛肉及び牛の内臓は、20ケ月齢以下と確認可能な牛由来であること。[2]全ての月齢の牛から特定危険部位(SRM)を除去すること。〕 米国及びカナダ政府から厚生労働省及び農林水産省を通じて提出された資料等を基に、我が国と米国及びカナダのBSE対策及びそれらの遵守状況について、以下の評価項目ごとに比較、検討を重ねてきました。平成17年11月2日から平成17年11月29日までの4週間、本審議結果(案)について、広く国民から意見・情報を募集いたします。なお、主な評価項目は以下のとおりです。
また、取りまとめられた審議結果(案)の結論部分では、米国・カナダ産牛肉等のリスク評価について、「米国・カナダに関するデータの質・量ともに不明な点が多いこと、管理措置の遵守を前提に評価せざるを得なかったことから、米国・カナダのBSEリスクの科学的同等性を評価することは困難と言わざるを得ない。他方、リスク管理機関から提示された輸出プログラム(全頭からのSRM除去、20ヶ月齢以下の牛等)が遵守されるものと仮定した上で、米国・カナダの牛に由来する牛肉等と我が国の全年齢の牛に由来する牛肉等のリスクレベルについて、そのリスクの差は非常に小さいと考えられる」とされたところです。
|
|
V-Q33.
|
米国・カナダ産牛肉等に係る食品健康影響評価審議結果案についての意見・情報の募集に寄せられた意見等の件数や概要について教えてください。(平成17年12月)
|
|
V-A33.
|
米国・カナダ産牛肉等に係る食品健康影響評価審議結果案についてのご意見・情報の募集は、平成17年11月2日〜平成17年11月29日に実施され、約8,800通のご意見をいただきました。
寄せられたご意見・情報の概要及びそれに対する回答につきましては、ホームページ (http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/iken-kekka/kekka-bse_usacanadian171208.pdf  )に掲載しておりますのでご覧ください。 )に掲載しておりますのでご覧ください。 |
|
V-Q34.
|
米国・カナダ産牛肉等に関するリスク評価の前提条件は輸出プログラムの確実な遵守だと思いますが、今後、委員会はどのように関わっていくのでしょうか。(平成17年12月)
|
|
V-A34.
|
食品安全委員会では、米国・カナダ産牛肉等に関するリスク評価において、輸出プログラムが遵守されていれば、米国・カナダ産牛肉等と国産牛肉等のリスクの差は非常に小さいとしたところです。このため、米国・カナダ産牛肉等の輸入に当たっては、評価の前提となった輸出プログラムの遵守の確保が重要であると認識しております。
輸出プログラムの遵守の確保については、リスク管理機関の責任において適切に対応されるものと考えておりますが、食品安全委員会としても、リスク管理機関に対し、遵守状況の検証結果についての報告を求めていくことにより、食品の安全性の確保を図っていくこととしております。 |
|
V-Q35.
|
米国・カナダ産牛肉の輸入が再開されて約1ヶ月で特定危険部位であるせき柱の混入が見つかり、輸入手続が一時停止されましたが、食品安全委員会としては、今後どのように対応していくのですか。(平成18年1月)
|
|
V-A35.
|
食品安全委員会では、米国・カナダ産牛肉及び内臓に関する食品健康影響評価について平成17年12月8日付けで、評価結果を厚生労働省及び農林水産省(リスク管理機関)に通知しました。その通知においては、米国・カナダ産牛肉等の輸入を再開する場合には、輸出プログラムの遵守の確保及び遵守状況の検証結果について、食品安全委員会への報告を求めるとともに、国民に対しても十分な説明を行うべきとしています。
平成18年1月20日、輸入時に米国から到着した牛肉の中にせき柱を含む子牛肉が確認された件については、同月26日の食品安全委員会会合において、リスク管理機関から、全ての米国産牛肉等の輸入手続を停止し、米国政府に対して、その原因究明と再発防止を求めている旨の報告を受けました。 食品安全委員会としては、今後とも、本件についての原因究明とその再発防止策の内容やそれを受けての両省の対応状況について逐次報告を求めつつ、食品の安全性の確保に尽くしてまいります。 |
|
V-Q36.
|
日本国内で、マトン肉を食べた場合、変異型クロイツフェルトヤコブ病に感染した例はあるのでしょうか。(平成19年8月)
|
|
V-A36.
|
国内外において、マトン肉を食し、変異型クロイツフェルトヤコブ病に感染した例は、現時点では報告されていません。なお、日本では、リスク管理機関により以下のリスク低減措置が講じられております。
めん羊及び山羊の伝達性海綿状脳症(TSE:Transmissible Spongiform Encephalopathy)対策として、平成16年2月に『と畜場法施行規則』を改正し、TSEの原因物質である異常プリオンたん白質が蓄積する部位である特定危険部位(12ヶ月齢以上の頭部(舌、頬肉を除く。)、せき髄及び胎盤並びにすべての月齢の扁桃、脾臓及び小・大腸(付属するリンパ節を含む))の除去及び焼却を義務化しています。 また、各都道府県において、牛と同様にと畜場におけるめん羊及び山羊を対象としたエライザ法(注)によるスクリーニング検査を平成17年10月から実施しており、現在まで陽性事例はありません。 さらに、BSE発生国からのめん羊及び山羊の肉等の輸入は、家畜伝染病予防法及び食品衛生法に基づき禁止されています。 |
|
(注)抗原抗体反応を利用した検査法の一種で、病原体などの有無を目印のついた抗体を用いて検査する方法。
|
|
V-Q37.
|
「我が国における牛海綿状脳症(BSE)の現状に関する食品安全委員会委員長談話」が7月31日に公表されましたが、BSE検査陽性牛と飼料規制の関係について詳しく教えてください。(平成20年8月)
|
|
V-A37.
|
我が国では、BSE対策の一つとして、平成13年10月より飼料規制を行っています。この直後(平成14年1月)に生まれた1頭の牛を除き、飼料規制以降に生まれた牛には、現在のところBSE検査陽性牛は確認されていません。
食品安全委員会は、平成17年5月に食品健康影響評価を実施しており、飼料規制や特定危険部位(SRM)除去などの対策が実施された結果、と畜場でのBSE検査について、全頭検査を継続した場合も、21ヶ月齢以上の牛のみの検査に変更した場合も、食肉のリスクはどちらも「無視できる」〜「非常に低い」と推定できると判断いたしました。 評価を行ってから既に3年以上が経過しており、改めてBSE対策について考える参考にしていただきたいという考えから、「我が国における牛海綿状脳症(BSE)の現状について」をとりまとめ、食品安全委員会委員長談話とともに公表しました。 詳しい内容は、食品安全委員会ホームページをご覧ください。 http://www.fsc.go.jp/sonota/bse_iinchodanwa_200731.html |
|
V-Q38.
|
我が国に輸入される牛肉及び牛内臓に係る食品健康影響評価(オーストラリア、メキシコ、チリ、コスタリカ、パナマ、ニカラグア、ブラジル、ハンガリー)に関する審議結果が出たと聞きました。どのような趣旨の評価なのか教えてください。(平成22年2月)(平成24年1月更新)
|
|
V-A38.
|
食品安全委員会では、平成17年に米国・カナダ産の輸入牛肉の食品健康影響評価を行いました。その後、「米国・カナダ産以外の輸入牛肉についてもリスク評価を実施して、可能な限り輸入牛肉等のリスクを明らかにする必要性がある」との消費者からの要望を踏まえ、食品安全委員会自らの判断により、BSE非発生国から日本国内に輸入されている牛肉及び牛内臓について食品健康影響評価を行ってきました。
これまでBSE感染牛が見つかっていない国で、平成15年〜18年度に輸入実績があった14ヵ国と他の家畜伝染病の関係で我が国への牛肉等の輸入が停止されている韓国を評価対象国とし、このうちオーストラリア、メキシコ、チリ、コスタリカ、パナマ、ニカラグア、ブラジル、ハンガリーの8カ国について食品健康影響評価の結果が取りまとめられました。 ※アルゼンチン、ニュージーランド、バヌアツの3ヵ国についても、平成23年12月に食品健康影響評価の結果が取りまとめられました。 今回の評価では、BSE発生国等から輸入された生体牛や肉骨粉が各国で家畜用飼料に使用された可能性や、各国の飼料規制の状況、特定危険部位(SRM)の利用実態、さらに食肉処理工程でのリスク低減措置の有効性など検討し、リスクを評価しました。 世界的にみてもBSEの封じ込め措置が有効に働き、BSEの発生頭数が著しく減少している状況下で、BSE非発生国を対象に、各国から我が国に輸入される牛肉等がBSEプリオンに汚染されている可能性についての絶対的な評価を行った点に特徴があります。 評価結果をとりまとめた8カ国については、いずれの国も「我が国に輸入される牛肉等がBSEプリオンに汚染されている可能性は無視できると考えられる」とされました。 今回の評価結果については、東京と大阪で意見交換会を行いました。配布資料及び結果については、食品安全委員会のホームページをご覧下さい。 http://www.fsc.go.jp/koukan/risk-bse2112/risk-bse2112-oosaka_tokyo.html 詳細な評価結果については、こちらを御覧下さい。 http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-hyouka-bse_world_k.pdf  http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-hyouka-bse_world_k2.pdf  また、季刊誌「食品安全」vol.22において、特集記事を掲載しています。 http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi/22gou/22gou_2.pdf 
|
|
V-Q39.
|
このたびBSE 対策の見直しに係る評価書が取りまとめられたと聞きましたが、今回の評価を行った経緯と評価結果のポイントを教えてください。(平成24年10月)(平成25年5月更新)
|
|
V-A39.
|
牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価について平成23年12 月、厚生労働省から以下の内容の諮問を受けました。
(1)国内措置(日本) ア 検査対象月齢 検査対象となる牛の月齢について現在の20か月齢超から30 か月齢超に引き上げた場合のリスクの比較。 イ SRM※の範囲 SRM のうち、頭部(扁桃除く。)、せき髄及びせき柱について除去する対象を全月齢から30 か月齢超に変更した場合のリスクの比較。 ※ SRM(特定危険部位)・・・BSE の病原体と考えられている異常プリオンたん白質が蓄積することから、流通経路から排除すべきとされる牛体内の部位のこと。 (2)国境措置(米国、カナダ、フランス及びオランダ) ア 輸入月齢制限 輸入対象となる牛の月齢を、 アメリカ、カナダ ・・・20 か月齢以下 → 30 か月齢以下 フランス、オランダ・・・輸入禁止 → 30 か月齢以下 に引き上げた場合のリスクの比較。 イ SRM の範囲 SRM のうち、頭部(扁桃除く。)、せき髄及びせき柱について除去する対象を全月齢から30 か月齢超に変更した場合のリスクの比較。 (3)上記(1)及び(2)を終えた後、国際的な基準を踏まえてさらに(1)ア及び(2)アを引き上げた場合のリスク評価 [1]平成24年10月22日の評価結果について 食品安全委員会では、諮問内容のうち(1)及び(2)について先行して、平成24年1月から同年9月までに8回のプリオン専門調査会を開催し、最新の科学的知見に基づく専門家の審議が行われ、9月10日の第446回食品安全委員会へリスク評価書案が報告されました。 その後9月11日から10月10日まで30日間のパブリックコメント(国民からの意見募集)期間中に寄せられた414件の御意見等について、10月12日のプリオン専門調査会で審議を行いました。これを受けて、第450回食品安全委員会(10月22日)において、“現行の飼料規制等のリスク管理措置を前提とし、牛群のBSE 感染状況及び感染リスク並びにBSE 感染における牛と人との種間バリアの存在を踏まえると、評価対象の5 か国の30 か月齢以下の牛由来の牛肉及び牛内臓(扁桃及び回腸遠位部以外)の摂取に由来するBSE プリオンによる人での変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)の発症は考え難い”とし、国内措置及び国境措置を諮問内容にあるように変更した場合のリスクの差は、「あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる」とする最終的な評価結果を取りまとめ、同日付けで厚生労働省に答申しました。 [2]平成25年5月13日の評価結果について 厚生労働省からの諮問内容のうち(3)については、プリオン専門調査会において日本をモデルケースとして評価手法の検討を行い、その評価手法に従い必要なデータが揃った国内措置の検査対象月齢のさらなる引き上げについて先行して議論が行われました。平成24年10月から平成25年4月まで5回のプリオン専門調査会を開催し、科学的知見に基づく専門家による審議が行われ、4月8日の第470回食品安全委員会へリスク評価書案が報告されました。 その後4月9日から5月8日まで30日間のパブリックコメント期間中に寄せられた91件の御意見等も踏まえて、5月13日の第473回食品安全委員会において「国内措置の検査対象月齢を48か月齢(4歳)超に引き上げたとしても人への健康影響は無視できる」とする評価結果を取りまとめ、同日付けで厚生労働省に答申しました。 なお、厚生労働省からの諮問内容の(3)のうち、米国、カナダ、フランス及びオランダに関する国境措置については引き続き審議中です。 <参考> さらに詳しくお知りになりたい方は、BSEに関する情報をご覧ください。 http://www.fsc.go.jp/sonota/bse_old.html |